台湾旅行で買うべきお土産!人気の烏龍茶8選 〜デパートからコンビニまで厳選紹介〜
台湾烏龍茶の基礎知識と魅力
台湾烏龍茶の特徴と種類
烏龍茶は半発酵茶の一種で、世界の茶葉生産量のわずか2%しか占めていません。この希少性と独特の製法が烏龍茶の価値を高めています。台湾はその重要な生産地として世界的に高い評価を受けています。
台湾では標高や気候、土壌などの自然条件が烏龍茶の栽培に適しており、長い歴史の中で独自の製茶技術も発展してきました。その結果、様々な種類の烏龍茶が生み出されています。
現在、台湾烏龍茶には包種茶、凍頂烏龍茶、高山烏龍茶、東方美人茶、鉄観音烏龍茶の5種類があります。
これらの種類はそれぞれ異なる製法と特徴を持っており、茶葉の収穫時期や発酵度合い、焙煎方法などによって風味が大きく変わります。これらの種類によって、使用される茶樹の品種も異なります。台湾の包種茶には青心烏龍、金萱、翠玉、四季春などの茶樹品種が使われています。ただし、これら4種類の茶樹は発酵度と焙煎度によって、異なる種類の烏龍茶に加工することも可能です。
茶樹の品種と加工方法の組み合わせにより、台湾烏龍茶は豊かな香りと味わいのバリエーションを持っています。各種類の烏龍茶はそれぞれ独自の魅力があり、好みや飲む場面によって選ぶことができます。
| 種類 | 特徴 |
| 包種茶 | 濃い緑色の色合いで、さわやかで上品な香りが特徴です。発酵度が低く、軽い味わいで初心者にも飲みやすい烏龍茶です。 |
| 凍頂烏龍茶 | 中焙煎や強焙煎を経ているため、より豊かな香りを持っています。凍頂山で生産されることから名付けられ、独特の花のような香りと甘みが特徴です。 |
| 高山茶 | 軽い焙煎か、あるいは全く焙煎せずに作られ、台湾人が最も好んで飲む烏龍茶です。標高1000メートル以上の高地で栽培されるため、爽やかな香りとクリアな味わいが特徴です。 |
| 東方美人茶 | 白毫烏龍とも呼ばれ、他の種類にはない蜜のような香りを持っています。特殊な製法と小緑葉蝉という虫に噛まれた茶葉を使用することで、独特の甘い香りが生まれます。 |
| 鉄観音烏龍茶 | 味が比較的濃いため、何度も淹れると逆に甘みが増してきます。中国福建省から伝わった品種で、独特の強い香りと深いコクが特徴です。 |
台湾の人々に愛される烏龍茶文化
台湾人がお茶を飲む文化は、18世紀に中国福建省からの移民がもたらしたことに始まり、その後の発展は主に商業的な理由によるものでした。福建省からの移民は自分たちの故郷の習慣や文化とともに、茶樹の苗木や製茶技術も持ち込みました。台湾の気候と土壌がお茶の栽培に適していたことで、茶葉の生産は急速に広がりました。
清王朝統治時代、茶葉は淡水港からの輸出額の90%を占める重要な産業でした。台湾茶、特に烏龍茶は欧米市場で高い評価を受け、重要な輸出品となりました。日本統治時代になっても、日本人はこのビジネスチャンスを認識し、台湾でのお茶産業の繁栄を継続させました。さらに日本統治下では、品質管理や生産技術の向上など、お茶産業の近代化も進められました。
興味深いことに、台湾人はお茶を飲む文化があったものの、1975年以前は一般市民はあまりお茶を飲んでいませんでした。なぜなら茶葉の経済的価値が非常に高く、価格も高かったため、当時はお金持ちだけがお茶を飲む習慣を持っていたのです。大部分の高品質なお茶は輸出用であり、一般の人々にとっては贅沢品でした。そのため、庶民の間では水や他の飲み物が日常的に飲まれていました。
1975年に世界的なエネルギー危機が発生し、台湾茶の輸出が中断されたことで、台湾烏龍茶は国内市場で再び中心的な位置を取り戻しました。輸出できなくなった高品質なお茶が国内市場に流れ込み、価格も下がったことで、一般の人々もお茶を楽しめるようになりました。この時期、台湾人は自国のお茶の素晴らしさを再認識するようになりました。
ちょうどその頃、1980年代に台湾経済が飛躍的に発展し始め、一般市民の可処分所得が増加したことで、茶芸館(茶藝館)が次々とオープンするようになりました。台北の「紫藤廬(しとうろ)」や台中の「陽羨茶行(春水堂の前身)」もこの時期に創立されました。茶芸館は単にお茶を楽しむだけでなく、伝統的なお茶の淹れ方や文化を体験できる場として人気を集めました。また、この時期には台湾独自のお茶文化が形成され、中国本土とは異なる台湾独自の茶文化が確立していきました。
1990年代には缶入り茶飲料が市場に登場し、「開喜烏龍茶」が台湾市場を席巻して炭酸飲料を上回り、市販飲料のトップになりました。これにより、お茶は若い世代にも広く受け入れられるようになり、日常生活の中でより身近な存在となりました。台湾人の挨拶も「食事はしましたか?」から「お茶でも飲みましょう」に変わり、お茶は台湾人にとって最も親しみやすく、最もよく飲まれる飲み物となりました。現在では、お茶は台湾の文化的アイデンティティの重要な一部となり、台湾人の生活と密接に結びついています。
日本人観光客に人気の理由
前述のように、日本が台湾を統治していた時代、日本人は茶葉ビジネスのチャンスを認識し、台湾でのお茶産業の繁栄を継続させるとともに、輸出商品としても活用しました。日本統治下(1895-1945年)では台湾茶の品質向上と生産効率化が図られ、台湾茶は日本国内でも徐々に知られるようになりました。
さらに1905年には、東京の銀座に台湾のお茶を提供する喫茶店がオープンしました。この店の看板商品が烏龍茶でした。当時の新聞によると、日本人はこうした喫茶店を「ウーロン」「ウーロン亭」「ウーロンチー」と呼んでいたそうです。この喫茶店の登場は、当時の日本人に台湾茶、特に烏龍茶の味と文化を紹介する重要な機会となりました。
この店は1910年に全盛期を迎え、最終的には1931年に閉店しました。約26年間の営業期間を通じて、多くの日本人に台湾烏龍茶の魅力を伝え、日本における台湾茶のイメージ形成に大きく貢献しました。
政治的な側面を別にすると、烏龍茶は第二次世界大戦が起こる前から、すでに「台湾の象徴」として日本人に受け入れられていました。永井荷風などの文人墨客もこの店を訪れていたといいます。こうした著名人の支持もあり、台湾烏龍茶は単なる飲み物を超えて、一種の文化的ステータスとして認識されるようになりました。
戦後の日本においても、台湾との歴史的なつながりや文化的な親近感から、台湾茶への関心は続きました。特に1980年代以降の日本での健康志向の高まりとともに、烏龍茶の健康効果が注目されるようになり、ペットボトル入り烏龍茶の普及も台湾茶の認知度を高めることになりました。
また、日本人が普段最も多く飲むのは緑茶で、烏龍茶は日本人にとって常に「外来品」でした。そのため、茶葉について少し知識のある人が烏龍茶を飲みたいと思えば、中国や台湾の烏龍茶を求める傾向があります。日本国内でも烏龍茶生産は試みられていますが、本場の味を求める愛好家は多く、台湾産の烏龍茶は特に価値が高いと考えられています。
このような背景もあり、台湾茶は日本人の間でさらに評判が高まりました。現代では、台湾旅行の際に烏龍茶やお茶関連の商品を購入することは、多くの日本人観光客にとって定番となっています。お土産としての人気も高く、台湾の茶芸館を訪れて本格的な台湾茶の淹れ方を体験することも、重要な観光アクティビティとなっています。
デパートで購入できる台湾烏龍茶5選
天仁茗茶の凍頂烏龍茶

(画像出典:天仁茗茶公式サイト)
南投県鹿谷郷の林鳳池氏が約100年前に福建省へ「挙人」の試験を受けに行き、合格して帰郷する際に武夷山から青心烏龍茶の苗木を持ち帰り、故郷の鹿谷に植えたことが台湾「凍頂烏龍茶」の始まりとされています。この苗木は現地の気候と土壌に適応し、独特の特性を持つ台湾特有の凍頂烏龍茶として発展していきました。
天仁茗茶の凍頂烏龍茶は、常に雲霧に覆われた台湾南投県の凍頂山地域で生産されています。この地域の優れた地理的環境のおかげで、品質が非常に高く、特有の香りを持っています。
収穫された茶葉は厳選され、伝統的な炭火を使って長時間かけて丁寧に焙煎されており、茶の味わいは甘く、まろやかで滑らかです。香りと喉越しの余韻を兼ね備え、何度も淹れても味が落ちにくいのが最大の特徴です。この持続性の高い風味により、凍頂烏龍茶は茶愛好家に特に評価されています。
天仁茗茶は台北の微風南山デパート、誠品南西デパート、新光三越南西店、SOGO忠孝デパートなど、多くの場所に販売店舗があります。
天仁茗茶の阿里山高山烏龍茶
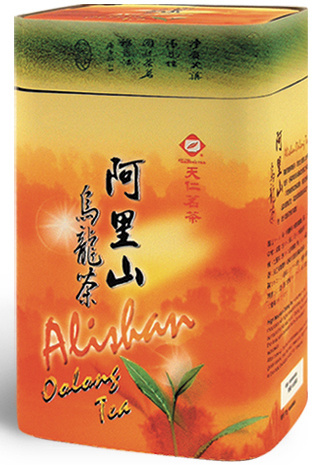
(画像出典:天仁茗茶公式サイト)
阿里山は台湾中部の嘉義県にある標高約2,000メートルの山岳地帯です。この地域の特徴的な地理条件と気候が、特別な品質の茶葉を生み出しています。朝霧に覆われた山々、きれいな水源、そして昼と夜の大きな温度差は、茶葉栽培に最適な環境となっています。
阿里山茶区の山からの湧き水で育てられる阿里山茶は、金色がかった蜜のような緑色の水色が特徴で、花の香りを含んだ上品な香りがします。甘くて濃厚な味わいの中に高山特有のさわやかな風味があり、台湾で最も有名な高山烏龍茶の一つです。
天仁茗茶の阿里山烏龍茶はこの有名な阿里山茶区で生産され、葉が厚く、ペクチン(果膠質)を多く含んでいるのが特徴です。お茶を入れると鮮やかな緑色で、蜜のような黄緑色の水色になります。味は甘くて濃厚、なめらかでコクがありながらも爽やかさがあります。上品な香りがあり、何度も淹れ直しができるのが最大の魅力です。
天仁茗茶は台北の微風南山デパート、誠品南西デパート、新光三越南西店、SOGO忠孝デパートなど、多くの場所に販売店舗があります。
ワンダーチュアンの東方美人茶

(画像出典:ワンダーチュアン公式サイト)
王德傳(ワンダーチュアン)は東京の日本橋にも店舗がありますが、特定の商品は台湾で購入するのが最も便利です。ワンダーチュアンの最高級東方美人茶は台湾の桃園・新竹・苗栗地域で生産されています。茶葉の選定と製造工程に細心の注意を払い、より多くの蜜蝶の「涎(よだれ)」が付いた茶葉を厳選しています。この特別な茶葉は小緑葉蝉という虫に噛まれることで独特の風味が生まれるのです。
このこだわりの製法により、より濃厚な蜜の香り、より目立つ白い産毛、より甘い味わい、よりなめらかな口当たり、より上品な香りを持ち、茶の質も豊かになっています。品質の高さから約10回ほど繰り返し淹れることができ、花の香り、果実の香り、蜜の香りが完璧に調和した味わいを楽しめます。
台湾でワンダーチュアンの東方美人茶を購入する場合は、台北の復興SOGO百貨店、台中の新光三越台中中港店、そして松山空港にも店舗があるので便利です。特に旅行の際には、現地で本場の味を求めてみてはいかがでしょうか。
羽曦堂の梨山烏龍茶
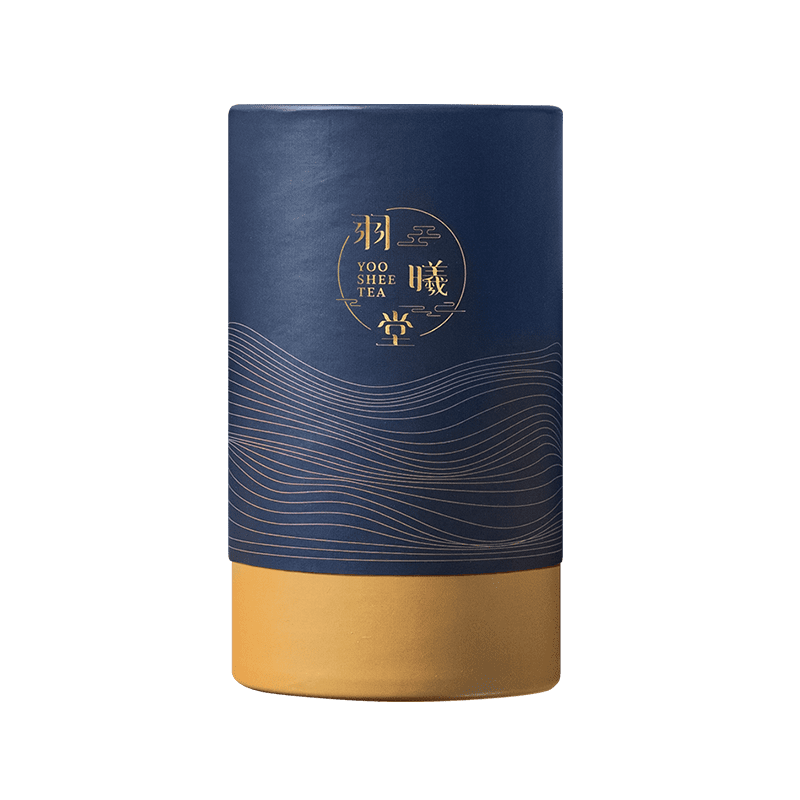
(画像出典:羽曦堂公式サイト)
羽曦堂の梨山烏龍茶は高山烏龍茶の一種で、南投県と台中市の境界にある梨山地域で生産されています。標高の高い優れた環境が、この茶葉に独特の素晴らしい風味をもたらしており、高山で手摘みされる高級茶の一つです。
梨山地域はお茶の生産が盛んなため、梨山の高山烏龍茶は台湾で非常に有名で、単に「梨山烏龍」と略して呼ばれるほどです。この茶葉は軽い焙煎と軽い発酵で作られ、日本の緑茶に近い製法が特徴です。そのため、普段日本の緑茶を好んで飲むけれども、まだ台湾烏龍茶を試したことがない方にも特におすすめです。
淹れると日の出のような薄い金色の水色になり、口当たりはまろやかで、夜来香(イエライシャン)の花のような香りが広がります。この独特の香りと味わいが、梨山烏龍茶の魅力となっています。
現在、羽曦堂は台北の信義区にある新光三越A4館に店舗を構えていますので、台北を訪れる際には立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
金品茗茶の貴妃美人茶
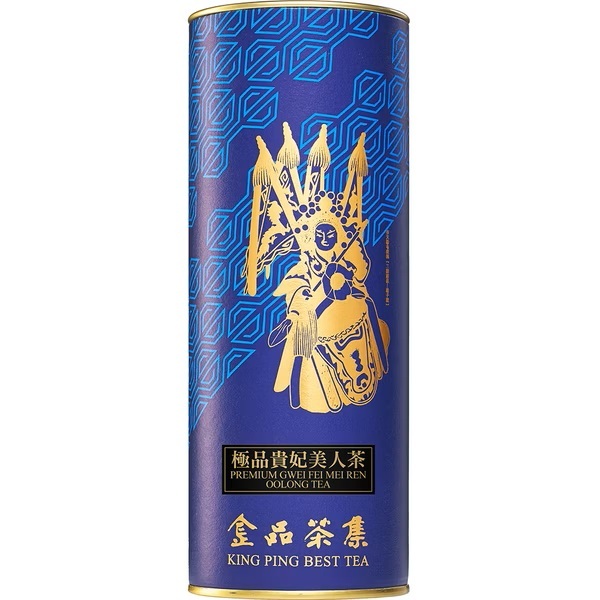
(画像出典:金品茗茶公式サイト)
貴妃美人茶の特徴は、主に製造工程が一般的な烏龍茶の製法と異なる点にあります。
凍頂貴妃茶は、より古い伝統的な凍頂烏龍茶の製法に従っており、屋外での萎凋(しおれさせる工程)の際に茶葉を太陽の下でやや長く置き、堆積発酵の時間も長めに取ります。このような製法によって、一般的な烏龍茶とは異なる香り、口当たり、風味が生まれます。貴妃茶には特別なタンパク質が含まれているため、淹れる際には水温を高くしすぎず、浸出時間も長くしすぎないように注意が必要です。
簡単に言えば、貴妃烏龍茶は伝統的な凍頂烏龍茶の「喉韻(のどごし)」と東方美人茶の「香醇さ」を兼ね備えており、台湾特有のお茶として、ぜひ試してみる価値があります。金品茗茶の貴妃美人茶は、琥珀色の透き通った水色が特徴で、濃厚な蜂蜜の香りと果実の香りが漂い、甘く滑らかな味わいが長く余韻として残ります。
金品茗茶は、台北101のB1階にあるMia C'bonスーパー内、欣欣百貨のB1階にあるMia C'bonスーパー内、そして桃園の中正国際空港第二ターミナルの免税区域の真向かいに店舗があります。台湾旅行の際には、この独特な味わいの貴妃美人茶を購入する機会として、これらの店舗を訪れてみてはいかがでしょうか。
コンビニやスーパーで手に入る台湾烏龍茶3選
ファミリーマートの桂花烏龍茶

(画像出典:ファミリーマート公式サイト)
台湾のファミリーマートでは「Fami Collection」というシリーズ商品において、玫瑰烏龍(バラウーロン)、桂花烏龍、阿里山金萱烏龍、翠玉烏龍、杉林溪高山茶、蜜桃春烏龍、阿里山高山茶、台東紅烏龍茶、凍頂烏龍茶など、様々な種類の烏龍茶が販売されています。
その中で特におすすめなのは桂花烏龍です。台湾ファミマの桂花烏龍は、百年の歴史を持つ茶荘「王德傳(ワンダーチュアン)」と共同開発された商品です。台湾の新鮮な桂花(キンモクセイ)を採集して作られており、桂花の香りは爽やかで上品、口当たりは繊細で喉越しも良いのが特徴です。
烏龍茶の清らかな風味と桂花の甘い香りが見事に調和しており、心身をリラックスさせるのに最適な選択と言えるでしょう。台湾旅行の際には、現地のファミリーマートで手軽に本格的な台湾茶を味わえる貴重な機会として、ぜひ試してみることをおすすめします。
ファミリーマートの翠玉烏龍茶

(画像出典:ファミリーマート公式サイト)
桂花烏龍茶のほかに、台湾のファミリーマートでおすすめの烏龍茶は翠玉烏龍茶です。こちらも百年の歴史を持つ茶荘「王德傳(ワンダーチュアン)」と共同開発された商品です。全工程において低温での抽出方法(コールドプレス製法)を用いて作られています。
翠玉烏龍茶は、玉蘭(ぎょくらん)や茉莉(ジャスミン)のような上品で穏やかな花の香りを持ち、味わいは清々しく爽やかです。また、茶の色合いの変化が明確で、蜜のような黄色の透明な水色が特徴となっています。
この翠玉烏龍茶は、日本ではなかなか味わえない台湾茶の風味を手軽に楽しめる貴重な商品です。台湾旅行の際には、桂花烏龍茶と併せて、この翠玉烏龍茶も是非試してみることをおすすめします。
開喜の凍頂烏龍茶

(画像出典:開喜公式サイト)
開喜烏龍茶は、一気に烏龍茶を庶民的な飲み物にした先駆けと言えるでしょう。開喜烏龍茶は、台湾らしさにあふれる広告によって一躍有名になりました。
凍頂烏龍茶には緑色のパッケージと茶色のパッケージの2種類があり、緑色は無糖タイプ、茶色は糖分を含むタイプとなっています。開喜の凍頂烏龍茶は、厳選された凍頂烏龍茶と紅烏龍茶を完璧に組み合わせており、澄んだ透明感のある琥珀色の水色が特徴です。味わいは清らかで甘く、後味に甘みが広がります。
また、余韻は濃厚でなめらかであり、独特の香りは爽やかで魅力的です。台湾を代表するペットボトル飲料として広く親しまれており、台湾のコンビニやスーパーで手軽に購入できます。台湾旅行の際には、高級な茶葉だけでなく、この庶民的な烏龍茶飲料も味わってみる価値があるでしょう。
台湾烏龍茶に関するFAQ
Q:台湾烏龍茶の賞味期限はどのくらいですか?
Q:台湾からのお土産として烏龍茶を持ち帰る際の最適な保存方法は?
Q:台湾には観光できる茶園はありますか?
多くの茶園では、茶摘み体験や製茶過程の見学、茶文化や歴史についての展示、そして茶葉の試飲や購入ができます。台湾の伝統的なお茶の文化や製法を直接体験できる貴重な機会となるでしょう。
観光茶園を訪れる際は、事前に予約が必要な場合もありますので、確認することをおすすめします。また、こうした茶園は公共交通機関ではアクセスしにくい場合がありますので、tripoolのチャーターサービスでの往復送迎、または時間制貸し切りチャーターの利用をご検討ください。再試行Claudeは間違えることがあります。回答内容を必ずご確認ください。





